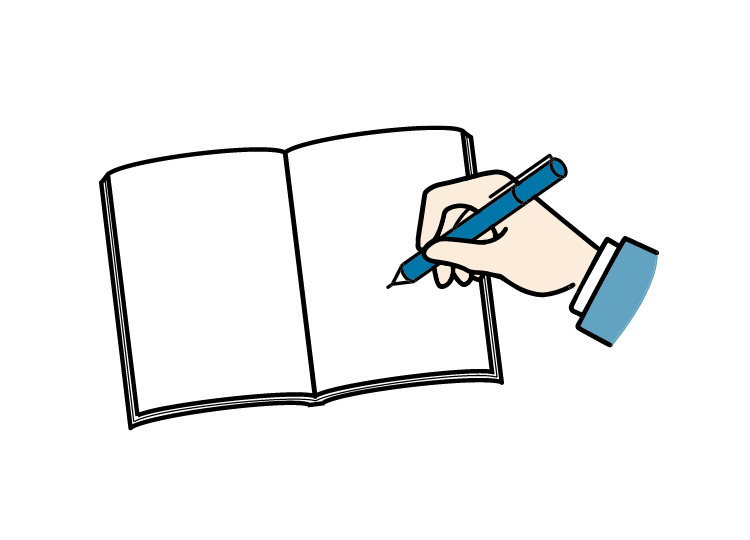
コラム
Columns
 #02
#02カスタマーハラスメント対策を通じて
誰もが安心して働ける社会へ
対応マニュアルの作成や対応に関する研修、従業員をケアする相談窓口の設置といった環境を整えることでカスタマーハラスメントから従業員を守る企業が増えています。特に、顧客と直接コミュニケーションを取るコールセンターや量販店では従業員の心身を守り、業務の効率をアップさせるためにカスタマーハラスメント対策が不可欠といえるでしょう。
ここでは、実際の企業の現場で、そうしたカスタマーハラスメント対策がどのように進み、効果を上げているのかをご紹介します。
ハラスメントを耐えてきた
オペレーター
顧客と直接コミュニケーションを取るコールセンターでは、ごく一部の顧客による不当なカスタマーハラスメントが問題となっていました。
オペレーターを悩ませていたのは「おまえじゃわからないから、上の人を出せ!」「お前の態度が悪い!」「苦情を入れるから、お前の名前を教えろ!」といった暴言を伴う通話。こうした通話を気にせず、「しょうがないな」で済ますことができればいいですが、ほとんどの人は恐怖を感じ、ダメージを負ってしまいます。
オペレーターの中には「自分がもっとしっかりと対応すれば怒らせなかった」と自分を責めてしまう人もいるとのことです。オペレーターに聞き取りをすると、こうした通話を受けた時の対処方法で最も多かったのは「我慢」。オペレーターは通話が切れるまで耐えることが多く、被害に遭ったオペレーターにとって大きな精神的負担になっています。また、カスタマーハラスメントによってオペレーターが疲弊し、退職につながってしまうこともあるとのことで、企業としてもカスタマーハラスメント対策は重要な課題となっています。
という新しい対応
現在、カスタマーハラスメントからオペレーターを守るために多くのコールセンターでは「通話の録音」や「複数人で対応する体制づくり」など、さまざまな対策が行なわれています。対策の1つとして、暴言や不当な要求をする顧客からの電話を切って、通話を終了させる「切電(きりでん)」という方法も考えられています。
「切電(きりでん)」の導入によって、カスタマーハラスメントと言えるような通話を、一定の要件に該当すれば、切ることも可能になります。もちろん、勝手に電話を切ってもいいという訳ではありませんが、顧客からの暴言に耐えていたオペレーターにとって「切ることができる」という選択肢が増えれば、状況は大きく変わります。
「切電(きりでん)」を導入した企業では、詳細に対応方針を作成し、基本的に丁寧な対応を遵守しつつも、「切電(きりでん)」が適用されるケースを明確に定義しています。
重大なカスタマーハラスメントを見逃さず、「切電(きりでん)」を実施することでオペレーターは、理不尽なことに我慢や無理をしなくて良いと感じ、安心して業務に集中できるようになるでしょう。また、不当な通話を切れるという安心感は精神的な余裕となり、オペレーターのスキルアップや定着率の向上にもつながるはずです。
「切電(きりでん)」の導入に見られるように、カスタマーハラスメント対策は企業と雇用者の信頼関係を強くし、労働環境を改善。社員が働きやすい環境づくりに大きく寄与していくことでしょう。
カスタマーハラスメントを
防ぐ
毎日多くの顧客と接する食品スーパーや量販店などの接客スタッフ。これまで日本では多くの接客スタッフが長時間立ちっぱなしのため、足腰を痛めるにもかかわらず「接客は立つもの」とされてきました。しかし、海外に目を向けると椅子に座って接客することは珍しくありません。
近年、接客スタッフの負担を減らし、働きやすい環境を整えるため、食品スーパーなどにおいて「座って接客」の導入が始まっています。接客時に働きやすい椅子が開発されるなど「座って接客」は徐々に広がる兆しを見せているのです。
一方、導入の壁になっているのが「顧客からの視線」。意見が分かれるかもしれませんが「立って接客しないのは失礼に見える」という印象を持つ方もいらっしゃるのも事実。そのため、導入企業では「座って接客」の趣旨を伝えるポスターやステッカーを作成し、店頭に掲示するなど理解促進を図っています。
しっかりと趣旨を伝え、理解を促進することで、新しい取り組みに向けられかねないカスタマーハラスメントを事前に防いでいるのです。また、広く告知することで「座って働けるなら、、、」とスタッフに応募する人が増えたという事例もあるとのことです。「座って接客」以外にも、従業員が体調管理のために、店頭で水分補給をすることを推奨しながら、店内ポスターの掲示や店内放送を通じて顧客の理解を呼びかける企業の取組もあります。こうした、働き手の健康などにも配慮し、サービスの見直しに取り組むことも、働きやすい職場環境づくりのために、大変重要な視点です。
対策で働きやすさがアップ
今回取り上げたようにカスタマーハラスメントの対策はネガティブな問題を解消するだけでなく、働きやすい職場環境づくりを実現できる取組となります。また、カスタマーハラスメントへの恐怖を解消することで働く人に余裕が生まれ、接客などのスキルがアップすることもあるでしょう。
人手不足に悩む企業にとって、カスタマーハラスメント対策がもたらす効果は、人材確保のために効果的な施策となります。こうしたカスタマーハラスメント対策を通じ、誰もが働きやすい、健康的な職場環境を実現して欲しいと思います。
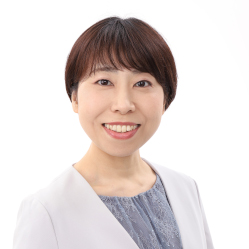
一般社団法人 日本ハラスメントリスク管理協会 代表理事